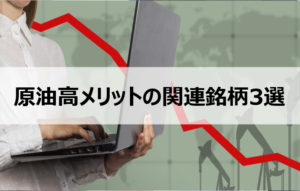必読必須の厳選3記事
スマホゲームの中でも極めて売り上げの高い「ソーシャルゲーム」いわゆるソシャゲは、ソーシャルネットワークサービスをプラットフォームに始まったゲームであることからそう呼ばれています。
PCにおけるブラウザゲームに近く、ゲーム自体をプレイするのは無料で、ゲーム内でのアイテムやキャラクターなどを手に入れるためにユーザーは課金を行います。
ただし、総ダウンロード数が急増してるからと言って売り上げと比例しているわけではありません。
どのような仕組みで収益を上げているのか?
スマホゲームの大ヒットで急騰した銘柄は?
という疑問について詳しくお答えしていきます。
目次
1.スマホゲームは収益性の高いビジネスモデル
「モンスターストライク」や「パズル&ドラゴンズ」などのスマホゲームは、多くのユーザーの少額課金により収益をあげています。
それぞれ2017年の1年間で500~1,000億円もの売り上げを誇りますが、ユーザーは学生が中心で、一人あたりの課金額はそれほど大きくありません。
テレビCMによって知名度を上げ、ゲーム内容が万人受けすることで多くの利用者を獲得。
数千円程度の比較的安い課金でも、欲しいキャラクターが手に入るといった設定にすることで、多くのプレイヤーから課金を引き出し収益をあげることができました。
反対に、一部ユーザーの高額課金によって収益を上げているスマホゲームもあります。
「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」といったゲームがこれにあたり、昨年230億円の売り上げとなりましたが、モンスターストライクやパズドラと比べてユーザー数は非常に少なく、そのほとんどが社会人です。
このゲームは沢山課金をしなければ欲しいものが手に入らないような仕組みとなっています。
しかし、その分手に入るものも限定・豪華など、他と比べて非常に価値のあるもので、毎月数十万円単位で課金をするような人も少なくありません。
2.スマホゲームの売り上げが爆発的な理由
– ユーザーが多い
誰しもがスマホを持つ時代となり、気軽に無料で遊べるアプリがたくさん出てきたことでゲームがより身近になりました。
そのため、老若男女の幅広いターゲットユーザーに向けてアプローチでき、現在では世界中に向けて配信することもできます。
– コストが低い
コンシューマーゲーム(市販の家庭用ゲーム機)では、グラフィックをいかに綺麗なものにするかなどの競争が続き、ゲーム開発にはかなりの時間とお金がかかります。
一方スマホゲームの場合、ゲームにより差はあるもののコンシューマーゲームに比べれば驚くほど安いコスト(開発費)での制作が可能です。
– 効率良く収益が得られる
コンシューマーゲームの場合は買い切りのため、ゲームの売り上げと言えばそれを売った際の一度きりでした。
しかし、スマホゲームだと毎月のガチャ更新など、イベントを開催することで定期的に収益をあげることが可能です。
新しいゲームを開発せずとも新キャラクターや新アイテムをアップデート(追加)していくだけでも、長期間それも飛躍的に収益をあげ続けることができる仕組みとなっています。
【厳選テンバガー狙いの銘柄を無料配信中!】
3.スマホゲームの大ヒットにより急騰した銘柄
– 【2121】ミクシィ
ミクシィは元々SNSの運営会社でしたが、そのサービスの売り上げが低下し、巻き返しを図るためスマホゲームに参入。
2014年に「モンスターストライク」が大ヒットした時、1,000円台だった株価が一気に5,000円台の5倍以上にも跳ね上がり、一躍スマホゲーム関連銘柄の存在を広めました。
さらに2017年6月には高値7,300円を付けており、その成長は凄まじいものとなっています。
– 【6758】ディライトワークス(ソニー)
ロールプレイングゲーム「フェイト・グランドオーダー」の莫大な売り上げにより、運営会社であるディライトワークスは営業利益が前年比31倍を記録します。
その利益の大部分は販売元のソニーが獲得し、2017年度第3四半期連結業績においてゲーム部門の大幅増収を記録。
初めはゲームの原作ファンを中心に一部のユーザーの高額課金により収益を得ていたものの、ゲーム自体の面白さから次第にプレイヤーの数が増えてユーザー層も多様化。
他の部門も好調であったことから株価の値上がりに繋がりました。
【厳選テンバガー狙いの銘柄を無料配信中!】
4.おすすめのゲーム関連銘柄
6-1.【7974】任天堂
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | その他製品 |
| 単位 | 100株 |
| 比較される銘柄 | ソニー, ホシデン, メガチップス |
| 注目ポイント | 世界的ゲームメーカー。ゲーム機「Nintendo Switch」をはじめ、「スーパーマリオ」や「ポケットモンスター」「ゼルダの伝説」などで知られる。 |
世界的ゲームメーカーの【7974】任天堂は、ゲーム関連銘柄としては絶対に抑えておかなければいけない銘柄です。
最新ゲーム機「Nintendo Switch」は世界的に大ヒットしており、「スーパーマリオ」や「ポケットモンスター」「ゼルダの伝説」といった主力ゲームソフトのブランド力は健在です。
1株あたりの価格帯が高いためやや手が出しづらい銘柄ですが、【7832】バンダイナムコとともに長期投資におすすめしたい安定したゲーム株です。
6-2.【9684】スクウェア・エニックス
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単位 | 100株 |
| 比較される銘柄 | カプコン, コナミHD, ガンホー |
| 注目ポイント | 家庭用ゲームソフト大手。2大国民的RPG「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」を手掛ける。 |
スクウェア・エニックス・ホールディングスは、「ドラゴンクエスト」と「ファイナルファンタジー」という2大国民的RPGで知られるゲームメーカーです。
2020年3月には、全世界待望となっていた「ファイナルファンタジー7」のリメイク版が発売されることから、業績を大きく押し上げることが期待されます。
日本を代表するゲームソフトメーカーとして、同じく国民的ゲームタイトルを多く持つ【9697】カプコンとともに抑えておきましょう。
6-3.【9766】コナミ
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単位 | 100株 |
| 比較される銘柄 | スクエニ, カプコン, マーベラス |
| 注目ポイント | スポーツ施設やカジノなど多角経営を進めるゲームメーカー。 |
人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」や人気野球ゲーム「実況パワフルプロ野球」で知られます。
同社はゲーム事業以外にも、スポーツ施設やカジノ事業にも力を入れており、「コナミスポーツクラブ」は日本最大のフィットネスクラブとなっています。
また、カジノ事業にも力を入れており、IR法案が成立したことでも期待されます。
5.まとめ
いつでもどこでも手軽にプレイできるため、ユーザーを爆発的に増加させたスマホゲーム。
今後も市場の成長は加速するばかりですが、すでにテンバガーを多く輩出しているセクターでもあるので、いよいよ無視できないほど巨大なマーケットと言えるでしょう。
実際に使ってみて、面白い!とか便利!使いやすい!といったスマホゲームやアプリがあれば、運営会社を調べて投資先の参考にするのもいいかもしれませんね。